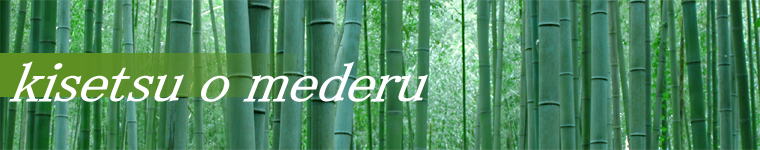
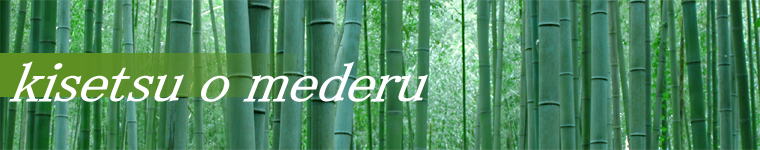 |
・ 懐紙(大目の束での持参が好ましい) ・ 楊枝(黒文字が使い易い) ・ 古帛紗、帛紗(お道具拝見の時)〈初心者はなくてもok) ・ てぬぐい又はハンカチ (着物の場合、袂にいつも用意があると便利、 ・ 足袋は席入り前に新しいものに変える(洋装の場合は、白靴下を持参し、履きかえる)
1 前石の上でつくばい、扇子を腰に差す。 2 右手で蹲踞の柄杓を取り、水をすくって左手をすすぎ、(蓋がある場合は右を左に開ける) 3 次に柄杓を左手に渡し、右手をすすぐ。 4 いま一度水をすくい、左手に水を受けて口をすすぐ。 5 柄杓を縦に持ち、左手を上、右手を中心に置き、静かに柄杓の残った水を右手を下方向に滑すようにして、水をきり、柄杓の柄を清める。 6 柄杓を元通りに直し、(口を左に横向きに置く) 7 懐中の手巾でぬぐい、席へ進む。
● 広間などの場合 1 手がかりが少し開けてあるので、膝前に扇子を置いて、(金目が右、木部が左)襖、障子を開けて席中を伺い、 2 扇子を前方に置いて、にじり寄って入る。(繰り返す) 3 扇子を持ち、立って、床前に進み、坐り、床の掛物に一礼の後、掛物を拝見し、 4 続いて、花、花入と拝見する。(風炉の場合は、香合も) 5 拝見が終われば、一礼して、右手に扇子を持ち、まず、両かかとを立て、左膝を立て、立って、身体の向きを変え、扇子の手を前にする。 6 そのまま縁を踏まぬよう、手前座へ向かい、風炉前に進む。 7 風炉、釜が据えられた正面に坐って、扇子を膝前に置き、釜、風炉、風炉の灰形を拝見する。(炉の場合は、棚があれば棚から拝見し、その後坐ったまま向きを変え炉を拝見する。) ・次客は床の拝見のすむころ、席入りをする。
1 両手をついてにじり出て茶碗を膝前に引きにじって帰り、茶碗を縁内に取り込む。 2 正客は茶碗を縁内次客の間に置いて、「お先に」と一礼する。 3 次に茶碗を膝正面、縁内に右手で置き、 4 きちんと手をついて「お点前頂戴いたします」と亭主に挨拶し、 5 右手で茶碗を取り上げ、左手にのせ、感謝の気持ちでおしいただき 6 正面をよけるため、時計回りに回し、いただく。 7 最後に啜い切りをし、 8 喫み口を、右手と人差し指で左から、右に拭き、 9 その指先は、懐中の紙で清める。 10 正面をよけた分だけ、前の逆に戻して, 11 縁外正面に置いて、拝見をする。 両手をついて、全体の形を拝見する。茶碗を手に取って細部を拝見する時は、両ひじを膝の上にのせ拝見する。 12 今一度、全体を拝見して、亭主の出された場所ににじりながら茶碗を進め返す。 ・
|